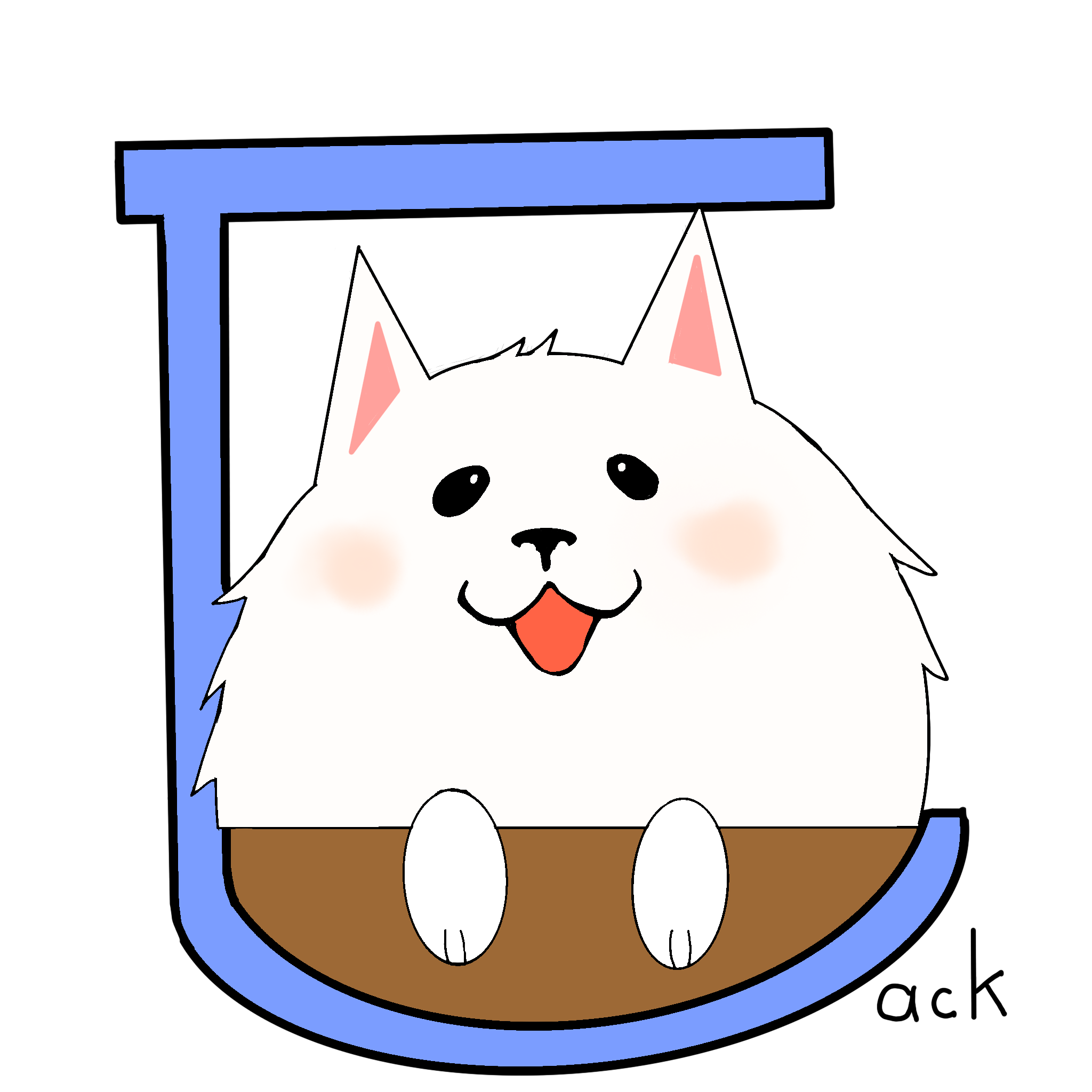「群馬県は昔の呼び方が違っていたって本当なの?」
本当です。
では群馬在住のわたしジャックジャンが群馬県の昔の名前についてご紹介します。
群馬県昔の名前について
群馬県の昔の名称とは
群馬県の昔の名称は「くるま」です。
名前の由来
上野毛国(かみつけのくに)のなかに車群(くるまのこおり)呼ばれる群があり、その場所がのちの群馬県になりました。
713年に好字令(地名を二文字にする命令)が発令され、上野毛国は上毛国、車群は群馬部に改変されました。
なぜ群馬に改変されたのか
好字令の発令により役人たちが作ったようです。
当時の上野の人達は馬に誇りを持っていました。
そこで役人たちは「群れる馬」の二文字で群馬を名付けました。
車群の由来とは?
当時の群馬にいた豪族の名前「車持(くるまもち)から地名になったそうです。
その豪族は天皇の送迎係だったそうで、馬を操縦する御者という役職でした。
また高崎市の十文字に「車持神社」という神社があり、その地は車の里と呼ばれていたそうですよ!
まとめ
群馬県は車がないと移動手段がない県ですが、その由来は昔からのものだったのだと感じました。
昔の名称がくるまというのも何かの縁を感じますね^^
以上、群馬県昔の名前についてでした。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここまでお読みいただきありがとうございました。